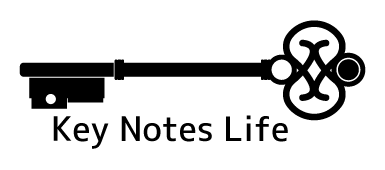身近な日常的な持ち物が武器になったり、護身用具になったりする事例がある。日本でもかつて杖、尺八、鉄扇などがそうであったが、とくに陸続きのヨーロッパで、たえず異民族との乳蝶や戦争を経験してきた人びとは、防衛に対して特別な意識をもっていた。種々の重厚な甲胃・武器のみならず、城壁をめぐらせた都市の構造、さらに鍵文化もそのあらわれであろう。ヨーロッパでは、指輪も護身用の武器として使用されたという事実がある。イギリスの作家マロリの『アーサー王の死』には、この指輪によって英雄が怪我を防止した話が載っている。その起源は、現在でもインドやモロッコ、ソマリアなどでみられる、防具としてのプレスレットやアームレットなどの大型リングにあるように思われる。これは一見すると装飾用に見えるが、いざという場合、身を守る武器の役割をも果たしている。
これらと類似したギザギザのある輪状のものが、イタリアからたびたび出土し、「古代ローマの剣士のリング」と名づけられている。しかし、美術史家で指輪研究者のパトケの説によれば、これは指輪にしては大きすぎるので、たぶん根棒と一緒に使用された武具ではないかと推測されている。さらにドイツ農民戦争時の実在の騎士、「鉄の爪ゲツツ」は、ゲーテの『ゲツツ』の戯曲でよく知られているが、武器としての指輪とは異なるとはいえ、彼の鉄の手がその役割を果たしている。
もっとも古いこの種の婚約指輪は、四世紀の後期ローマ時代のものである。これは宝石入りの三つの指輪の繋がっためずらしい形状をしており、墓から出土しているので、武器というより、護符として死者とともに埋葬されたものと考えられている。さらに南部ドイツおよびティロル地方で、中世以降、農民が使用していたとおぼしき多数の防具用(武器)としての指輪が残っている。材料は鉄、鉛、鋼、真鏡、銀などのものが多い。これは「ベルリン民俗博物館」に所蔵されているが、なぜこれだけ多く残っているのか不思議なほどである。おそらくふだんは護符として身につけていたのではないかと推測され、何らかの理由でこれが農民のあいだで流行していたのかもしれない。というのも、防具指輪のモティーフには、聖アントニウスの肖像がよく用いられており、この聖者は「予期せぬ死に対するパトロン」として、人びとの信仰を集めていたからである。
本来の攻撃用武器としての指輪を好んだのは、血気盛んな若者であった。かれらは相手からの攻撃、喧嘩、学生の決闘あるいはブルシエンシャフトの蜂起のときに、実際使ったという。いずれにせよ、これは男性の持ち物であった。とくに中世以来、学生の決闘は日常茶飯事であって、剣のほかに典型的な武器として、親指以外の四本の指にはめる鉄拳のリンがある程度知られている。これは防具指輪の変形であるが、その武器が実際のところ顔面にたった場合を想像すると、いささか背筋がぞっとする。以上のように、この種の指輪は一見すれば、装身具としてカ今ラージュすることができ、いったん何かあると武器になった。とくに相手が無防備の場合、素手より圧倒的に有利であった。この点からも、やはり長い指輪の文化を有するヨーロッパでは、万一に備えて自己防衛のために気を配っていたことが分かる。