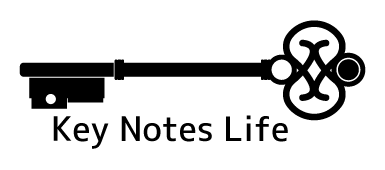中世の大学では、博士の称号を取得した記念として、指輪の授与がおこなわれていたという記録がある。またルネサンス時代には、皇帝や国王が詩人を顕彰する際に、「詩聖冠」とともに指輪を贈っている。このような記念指輪は、戴冠式、同盟成立記念、戦勝記念、褒賞などの際や、個人的な誕生日、出産、結婚記念、死亡など、通過儀礼の節目にもつくられたりしている。多様な記念指輪のなかでも、ここではとくに死と関係ある特異なものを採りあげる。死者とのかかわりにおいて注目すべきものは、「メメン卜・モーリ」(死を忘れるな)という装飾指輪であって、十四世紀以降にあらわれている。これは開館や骸骨など死体をモティーフにしたものであり、葬儀の後、死者の思い出のために、関係者に配られている。すくなくとも日本人の感覚では、これらのモティーフを身につけるという発想はない。むしろそれを縁起の悪いものとして、忌み嫌う風潮がつよい。この差はいったい何に起因するのであろうか。ここにヨーロッパ人における死との特別なかかわり方があるように思われる。
十四世紀のはじめ、ヨーロッパは天候不順によって大飢鐘に見舞われ、多くの死者を出した。さらにイングランドとフランスの百年戦争、二二四八年からヨーロッパで大流行したベストなどによって、死は日常生活のなかに入り込み、「鞭打ち苦行」、「死の舞踏」という特異な集団行動を引き起こしている。こうして自分の体を鞭で故意に傷つけたり、死者や骸骨を克明に描くことによって、人びとは死を直視し、かつ死の恐怖から逃れようとした。もともと死は、寄る辺ない人間にとって、避けて通れないものであったが、キリスト教がヨーロッパの人びとのこころを捉えた理由のひとつに、この宗教の説く死後の世界への安らぎがあったといえよう。
キリスト教の教えでは、現世の行状によって死後、天国か地獄へ行くことになっていたけれども、十三世紀以降、その中聞の煉獄という領域が設けられ、罪を犯したものでもここで償えば天国へいけるとした。当時から巡礼が流行し、人びとはあの世のしあわせを願って、難難を乗り越え、ローマ、サンティアゴ・デ・コンポステラ、果てはエルサレムまでも意を決して巡礼に出かけている。こうして現世よりも死後のことを考える気持ちは、死を身近なものにしたし、死への愛着の念すら生みだしている。これは当時の絵画や図像にはっきりとあらわれており、とくにこの風潮は中世だけでなく、ルネサンス期の美術にまで広がっていた特徴でもあった。